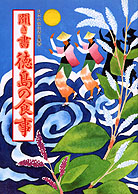聞き書 徳島の食事 那賀奧の食より
■夕飯―ひえ飯、ひえろうすい、干し大根の煮菜、炊いたずきいも、漬けだいこ
雪でも降りそうな寒い日には、ずきいもやしゃくしな、しいたけ、ねぶか(ねぎ)など、あるものをなんでもなべに入れ、味噌で味をつけたひえろうすいを炊く。だしをとるのに入れたいりこもそのまま具になる。冷えきったからだには温かいろうすいがなによりである。
この「ろうすい」は「ぞうすい」がなまったものだということで、女衆や子どもは「おみいさん」と呼んでいる。
夜なべ仕事には、男衆はわらぞうりを編む。日暮れまではなんやかやと外の仕事をし、家に帰ると女衆が夕飯の用意をしている間に、わらを打つ。夕飯を食べてからだが温まったら、いるり(いろり)の端に座って再び夜がふけるまで、足半ぞうり(足裏の半分くらいの大きさのぞうり)を編む。稲わらは、蝉谷では手に入らないので、一里ほど離れた山すその出原や助村で、気安い人に分けてもらう。
写真:冬の夕飯
上:漬けだいこ、梅干し、干し大根の煮菜/下:朝のひえ飯、味噌味のひえろうすい(ひえ、ずきいも、しいたけ、ねぶか、菜っぱ入り)
出典:立石一 他編. 日本の食生活全集 36巻『聞き書 徳島の食事』. 農山漁村文化協会, 1990, p.121-123