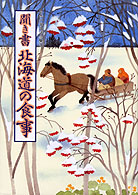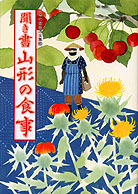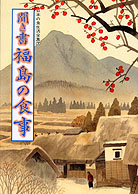もくじ
べこもち
聞き書 北海道の食事 西海岸にしん漁場の食より
五月の端午の節句の食べものは、にしん漁で忙しいときには日延べして、五月下旬か六月上旬につくる場合もある。
うるち米を三、四時間うるかしてから水をきり、臼と杵で搗いて粉をつくる。粉はふるいにかけてきめの細かい粉にする。粉のほぼ半分は黒砂糖を溶かした汁でこね、残りはお湯と白砂糖を加えてこねあげておく。これをかしわの葉などの模様をくりぬいた木製のべこもち型に入れて形をつくる。このとき、黒砂糖入りの黒と白砂糖入りの白を半分ずつ使い、二色にする。さらにこれを、せいろに並べて蒸す。四〇分ほど蒸し、もちの表面につやが出てきて、指でさわってみて弾力があれば、蒸しあがりである。
できあがったべこもちは皿にとって食べるが、近所に配るものは、笹の葉やかしわの葉に包むこともある。

笹巻き
聞き書 山形の食事 県北最上の食より
五月五日の男の節句には笹巻きをつくる。もち米一升で、だいたい七〇個の笹巻きができる。
水に一晩浸しておいたもち米をざるに上げ、水気を切っておく。笹の葉二枚を裏合わせにして三角の形をつくり、もち米を詰め、余っている笹でふたをし、みのげ(すげの一種。みのの材料となる草で、乾燥させて使う)でしっかり結ぶ。それを五つくらいまとめて一つにつるせるようにし、大きななべにたっぷりの湯を入れて三〇~四〇分煮て一〇分くらいそのまま蒸らす。
ざるにとり上げ、横棒に下げて冷ます。きな粉をつけて食べる。笹巻きは保存がきくので、都会にいる子どもたちへ送ったりもする。

笹巻き
聞き書 山形の食事 県南置賜の食より
五月、端午の節句につくる。新暦の五月五日はまだ笹が大きくならないから、旧暦の五月五日にお祝いする。
笹を山からとってきて、たっぷりの水で笹と笹巻きを結ぶすげを煮て、水にさらしておく。もち米一升を結ぶのに笹は一〇〇枚くらい用意する。
前日もち米をよく洗い、水に浸しておく。もち米をざるに上げ、水を切る。笹もざるに上げ、水気を切る。一枚の笹を丸くくるっと巻いて三角の形にまん中をとがらせ、その三角にもち米を入れる。笹の葉のつけ根のほうをふたのようにして折り、その上にもう一枚の笹の葉をかぶせて、三角の形につくる。
米の詰まった、形の整った笹をすげで結う。五つずつ一束に結び、二束を合わせて一〇個にする。もち米一升でだいたい四〇個から五〇個できる。
大きななべに入れ、たっぷりの水を入れて一時間半から二時間くらい煮る。煮えたらなべからとり出して三〇分くらい蒸らす。
三角にした笹にもち米をあまりぎっちり詰めると、煮ているうち米がふえてはみ出すから、少しゆとりあるように詰める。
笹巻きの食べ方は、黒砂糖に少し水を入れ、火にかけてとろりとさせたものに、笹をむいた笹巻きを入れてよくまぶし、それからきな粉にまぶし、あべかわにして食べることが一番多い。ときには納豆をつけて食べることもある。またなにもつけずに白いまま食べると、笹の香りがしてうまいという人もいる。
神さまや仏さまにも、あべかわにして供えることが多い。宵節句には笹巻きを食べるならわしになっている。

かしわもち
聞き書 福島の食事 福島南部の食より
五月節句やさなぶりのときにつくる。
小豆を煮てこしあんをつくり、黒砂糖で味つけをする。
うるち米の粉五升に、もち米の粉一升五合を入れ、よく混ぜる。粉の中に熱湯を入れてよくこね、ちぎって平らな丸形にのばし、あんを入れて二つ折りにしてかしわの葉で包み、せいろでふかす。

出典:矢島睿 他. 日本の食生活全集 1巻『聞き書 北海道の食事』. 農山漁村文化協会, 1986, p.238-239
出典:木村正太郎 他. 日本の食生活全集 6巻『聞き書 山形の食事』. 農山漁村文化協会, 1988, p.124-124, p.175-176
出典:柏村サタ子 他. 日本の食生活全集 7巻『聞き書 福島の食事』. 農山漁村文化協会, 1987, p.194-194