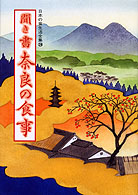聞き書 奈良の食事 十津川郷の食より
■昼飯――麦飯、つぼきりさえれの焼いたの、しめじ汁、なすびの塩漬、味噌
大谷家では、日傭宿といって、上湯川のかり川で働く人たちをときどき大勢泊めている。日傭宿をした日は三〇~四〇人ほどの弁当を川まで届ける。そんな日は麦飯を一斗ほど炊く。どぶ酒(どぶろく)をつくるのも日傭師さんのごはんが余ったりしたときで、家で花をたてる(こうじをつくる)こともあるし、平谷から「こうじの素」(米こうじ)を買ってきて仕込むこともある。
山からはしめじが負いかごにどっさりとれるので、家族の昼飯や日傭師さんの夕飯の菜として、四升釜にいっぱいしめじ汁をつくって菜にする。
月に二回くらいの割で、紀州(和歌山県)の田辺などから海の魚の塩もの、干ものなどを担うて物売りが山越えしてやって来る。物売りが来た日は、つぼ切りさえれ(背開きの塩さんま)の焼いたのが菜につくこともある。一人四分の一切れほどで、子どもらは「頭のほうがいい」「しっぽのほうがいい」と大さわぎし、親は「早う食うな、もっとゆっくり食えよ」と叱りつけたりする。
田辺から来た物売りは、帰りにはび(まむし)、わり菜、ふしの実(うるしに似た木の葉先にできるこぶのようなもの。染料用)、しいたけのじゃみ(くず)を買って帰る。
写真:秋の昼飯
上:つぼ切りさえれの焼いたの、なすびの塩漬/下:麦飯、しめじ汁
出典:藤本幸平 他編. 日本の食生活全集 29巻『聞き書 奈良の食事』. 農山漁村文化協会, 1992, p.268-270