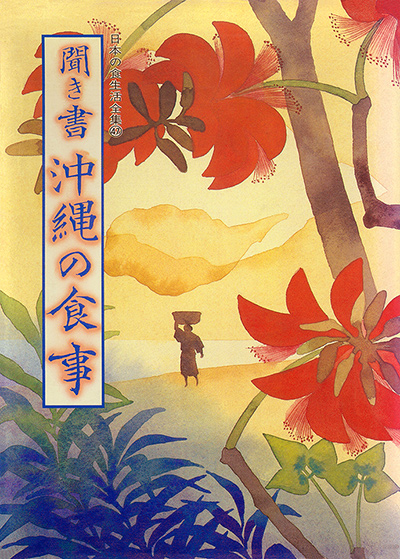聞き書 沖縄の食事 宮古の食より
■お盆
十三日の迎え日は、神棚と家の内外の掃除をしてお供えものをする。さとうきびを約一尺八寸に切ったものを杖の代用として、神棚の左右に二本ずつ立てる。また、三寸ほどに切ったものを八本束ね、あだんの実、バナナ、みかん、ばんじろうなどとともに、三方または重箱二つにのせて供える。
日が暮れて薄暗くなるころ、たかきびの脱穀した穂稈でたいまつをつくって門の両側にともし、線香を焚いて精霊を迎える。入口にはおわんに水を入れて置き、精霊に手足を洗ってもらう。そのあと神棚に案内し、お茶、お茶うけ、さたぱんびん(黒糖てんぷら)を供えたあと、お酒と魚なます、ごはん、揚げ豆腐、ぱんびん、砂糖と醤油で煮しめた豚肉、野菜の煮ものなどを大皿に盛り、そのほか豚骨汁と、やするばぎ(ねこはぎ)の幹でつくったおはしを添えると、神棚にいっぱいになる。家族一同が焼香して拝む。
十四日を中日といい、この日はごはん、ぱんびん、豚肉の煮つけ二切れを中皿に盛り、線香を持って親族の家を回り、お焼香する。
十五日は、迎え日にお供えしたものをとりかえたり、塩水で洗い直して供える。お昼には必ずいもとぴーすな(すべりひゆ)のあえものを供える。
晩はお正月の十六日祭り同様、おもちや重詰料理を供え、紙銭(あの世で使うお金)を焼く。重詰料理は、魚のてんぷら、揚げ豆腐、結びこんぶ、ごぼうの煮しめ、豚肉の煮つけ、かまぼこなどである。
午前〇時ごろ夕小昼を供え、焼香する。そのあと供えものからおはつをとって(一切れずつとって)、子孫がいなくて供養してもらえない精霊のつと(みやげ)にする。女が頭にものをのせて歩くとき使う、わらで編んだ丸い輪のかうすも神さまの数だけつくって供える。このかうすにつとをのせて持っていっていただくためである。花生け、香炉など、神棚に供えたいっさいを宅地外に運び、道の側に置いて精霊を送る。
写真:お盆の供えもののひとつ、魚なます
出典:尚弘子 他. 日本の食生活全集 47巻『聞き書 沖縄の食事』. 農山漁村文化協会, 1991, p.213-215