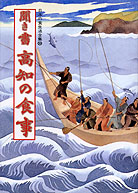聞き書 高知の食事 香長平野の食より
皿鉢料理には必ずぜんざいを入れた鉢が出され、子どもの座りそうな末席のあたりに置いてある。小豆が汁たっぷりに甘く煮られたぜんざいは、子どもや年寄りが喜ぶのはもちろんだが、さんざん飲んだあげくの上戸が、鉢の近くへ寄ってきて「あし(わし)にもひとつぜんざいを入れとうせ(入れてください)」という。口がかわっておいしいのだろう。ぜんざいのような汁けのものでも、刺身でも、すべて小皿にとるのだから、少ししか入らないわけで、口がわりにはちょうどよい。
寒中にさらしておいたもち粉で小さいだんごをゆでて入れるが、それがなければすまきを薄切りにして入れる。ほうぼうや鯛の丸ゆでを、姿のままずっぽりと浸しておくこともある。
ゆでてだしの出てしまった魚に甘みがしみこんで、ごはんのおかずの塩のきいた魚とは違い、小豆味の魚になる。
写真:魚を浸したぜんざい
皿鉢料理のひとつ。丸ゆでした魚をぜんざいの中にすっぽり浸しておき、甘みのしみこんだところで食べる。
出典:松崎淳子 他編. 日本の食生活全集 39巻『聞き書 高知の食事』. 農山漁村文化協会, 1986, p.67-67